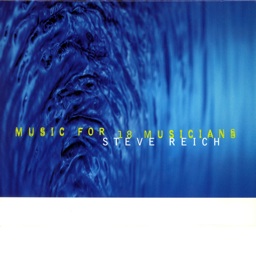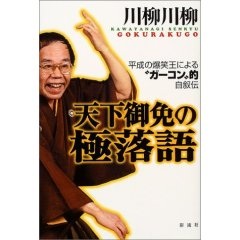Archive for the ‘日記’ Category
5m先の帽子姿
オペラシティコンサートホール
「スティーブ・ライヒの音楽」
『Drumming (Part 1)』
『Proverb』
『Music for 18 Musicians』
配置転換,アイコンタクト,そしてその際に時折浮かぶ笑顔。人間が演奏しているという当たり前の事実に感極まる。『Drumming (Part 1)』では演奏者同士のマレットがぶつかる音までもが愛おしい。
『Music for 18 Musicians』。心躍るのはCDで聴いていたのと同じSection Vから。一音ずつ増えていくピアノを数え続ける昂揚と,それがパルスに溶け込む瞬間の陶酔。両足を広げて振り続けられるSection VIのマラカスの存在感はCDではわからなかった発見。
意外なまでに若い聴衆層もあってか,叫び声の飛び交うスタンディングオベーション(誰も「ブラボー」なんて言いやしない)。それでもこの演奏を体験した後では自然な感情の発露として全くもって正しく思えてしまうから不思議。作法を超えた原初の行動欲求。これが野外フェスだったら踊る姿も見られたかも。
寄席と思えば腹もたつまい
エルメスギャラリーで,最終日のSarah Sze展。
何度訪れても新たな発見。広大な世界の中に数多く存在する微少な世界と,そこで同時多発的に繰り広げられる秩序と混沌。現出した『塊魂』。
思考と行動のエアポケットに入った瞬間,十和田市現代美術館で覚えた自分でも驚くばかりの憤りが首をもたげる。そこで浮かんだひとつの解は,美術館は寄席の定席だと考えれば良いのではと。
動線に従って巡る常設展は,さしずめ番組表に沿って次から次と高座に上がる噺家を見るようなもの。全ての噺家が心の琴線に触れるわけがないのと同じように,美術芸術だって相性の良し悪しはあろうものよ。そう,今回はたまたまあわない噺家が多かっただけの話。それでも寄席同様に予期せぬ嬉しい出逢いもあったのだから,その他大勢を酷いと嘆くよりも,素晴らしいと思った作品と作家を今後は追っていけば良いだけ。そう,寄席で興味を惹かれた噺家の独演会に足を運ぶ流れと同じ。
独演会と言えば。
常設展を寄席の定席と考えるならば,特別(企画)展は同日同場所で開催されている独演会。己の嗜好を知った上で足を運ぶ/運ばないを選ぶものだけに,未知なるものとの邂逅を求める気持ちが強すぎてもいけないのかも。また,せっかく訪れたのだからというもったいない意識も良し悪し。関心が無いのであれば見ないという選択も時には有効であることも今回の収穫。
回文の男
横浜と大阪,どちらが近いと言われれば,やっぱり横浜。東京-新大阪の約1/3の時間で「横浜にぎわい座 第十七回 上方落語会」到着。
皆さんお初の中,お目当てはもちろん笑福亭福笑。高座を拝見することが出来ただけでも満足なくらいだが,サゲに向かって仕掛けをはり続ける『千早ふる』,指数関数的にどこまでもテンションが上がり続ける『もう一つの日本』,そのどちらも笑いが絶えず。ときおり顔を覗かせる黒い一面もまた好み。師匠と弟子,どちらも好きという組み合わせは多いけれど,福笑・たまはその中でもちょっと抜きん出た感あり。
その他の方々もファーストインパクトを差し引いても素晴らしい出会い。上方なので上野ではなく梅田に向かう,桂ちょうば「いらち俥」。”寝起きのジュリー”桂三若(確かに似てたなぁ)の大阪人独り舞台「ひとり静」,そして器用富豪とでも表現したらよいのか,次から次に繰り出される手作りの飛び道具に唖然となった笑福亭鶴笑「パペット落語 立体西遊記」(林家しん平との東西器用富豪二人会が見てみたい。演目は孫悟空vs骸骨かっぽれで是非)。どこまでも貪欲に笑いを狙う姿勢の数々,知らない世界はまだまだある。
二 九 三 八 十
初めて盛岡以北の新幹線に乗り二戸。そこから車で九戸→三戸→八戸。更にここまで来たのならばと十和田まで。
十和田市現代美術館。
作品・建築・人(スタッフ・来場者),そのどれもが何か浮き足立っているような感覚。全てがもう少しこなれてから足を運ぶべきだった。
それでもHans Op de Beeck「Location (5)」との出会いは唯一にして大きな幸せ。漆黒のダイナーと窓の外に広がる無機質なハイウェイ。『ロスト・ハイウェイ』を思わせるアメリカン・ノワールな景色。自分がアートに求めているのはやっぱり空間体験なんだ。白く軽い建築の中に黒く重い世界が内包されている対比と差異の強調もまた。
最後にカフェで一休み,幅の狭い通路からドアを手前に引いてトイレへ。外へ戻る際,ドアを押そうと手を伸ばすとそこには一枚の貼り紙。「ドアの外に人がいます。静かに開けてください」。確かにあの幅の通路で押して開ければぶつかるかもね。最初から横引き扉にするのではなく,他者をおもんばかる気持ちを喚起させる。その建築的配慮,有り難いことです。
ひばり鳴く路地裏
めずらかな番組
2週間かけてBShi『立川談志10時間スペシャル』完走。
週末毎の電車移動時間,そしてiPod touchが無ければ挫けてたよ。
過去に放送された番組の再利用もあったので,未見だったのは7時間くらいか。落語会からの噺(六席)もいいんだけど,やっぱりおもしろいのはこの特番用として新たに作られた部分。なかでも瞠目は家元・正剛のW松岡対談。噛み合っているようないないようないるような,何とも不思議なやりとり。童謡から始まって正剛さんらしい日本語論,最後は富岡鉄斎を引き合いに老いて花咲く希望で〆。
第二部で立川志の輔が語っていた,ダンカン(談かん)の立川流からたけし軍団への移籍エピソード。どこかで聴き覚えのある話だなと記憶を手繰ると,10月にフジテレビで放送された『真夜中はピクニック』。
深夜3時,吾妻橋に集合した笑福亭鶴瓶・立川志の輔・春風亭昇太が,浅草・上野・日本橋と歩きながら数多の噺家の逸話を述懐。松鶴・談志・柳昇・小さん・米朝・川柳・福笑・可朝…。鶴瓶の語る福笑の全裸ヨガに息が出来なくなるほど笑い,今ではそこから弟子のたまに関心が波及,落語会に足を運ぶことに。全く,何がきっかけになるかわからないもの。
帰宅後,予約録画しておいた「くるり with ウィーン・アンバサーデ・オーケストラ ふれあいコンサート ファイナル」を。ウィーン熱再燃。あの博物館,この美術館,その図書館のキーワード化を考えたり,再訪の時を思いながらドイツ語の教科書を改めて開き直したり。
元気(で酔っぱらい)のほうの福田康夫
骸の履歴書
青木画廊「江本創 H博士の異形の愛情」
最終日,滑り込み。
初めて生物以外で拝見した茸標本の虜。思わず笑みこぼれる小さな仕掛けにも,細部に宿る何かを想う気持ちが伺える。
東京大学総合研究博物館「鳥のビオソフィア―山階コレクションへの誘い」
こちらは初日。
いつもと同じ気持ちで建物に向けて歩を進めると,視界の先に見慣れない極彩色の何か。館内に入っても新たな動線など変化は続く。そこに忽然と現れた驚異の部屋。ここはハレかザルツブルクか。驚きは展示物だけに留まらず。畏怖覚える展示内容を記す硬質な文。体につけられた標本タグは「骸の履歴書」。今日は所を変えながら履歴書を読んだ一日ということ。
動線変更はあの驚異の部屋に至るまでの視線変更。それに気づいたのは極彩色の何かを背にした後のことでした。